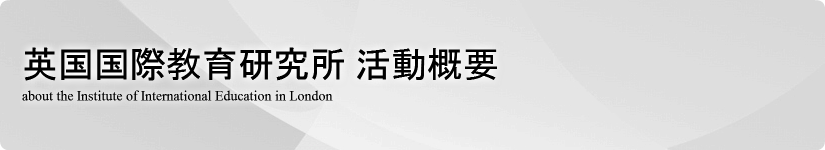検証
教育に関わるさまざまな問題について、図師照幸所長が徹底的に分析し、斬新かつグローバルな視点から提言します。
No. 30 子どもたちに今、何が必要なのか その5 母親(5)
ぼくは漫画「サザエさん」のファンである。日本にいるときは第一巻から百巻を超えるまで全部コレクションしていたが、友人たちに貸しているうちにいつの間にかその全集が揃わなくなってしまった。
「サザエさん」を読んでいて気持ちがいいのは、そこに登場する人たちの言葉遣いの清潔さである。必要以上に丁寧ではなく、かといって下品な乱暴さがない。確かな生活人としてのしっかり中身の詰まった言葉の質感を感じさせるのだ。
新しい洋服を着た舟(フネ)が夫の波平にその感想を尋ねる。
「あなた、いかがですか?」
大掃除中のサザエには、
「ごくろうさま。お茶がはいりましたよ」
この種の言葉遣いにはもはや、外国人が学ぶ日本語の教科書でないとお目にかからないかもしれない。そのため、こんな言葉遣いは不自然だという感想をもたれるかもしれないが、たとえばぼくが子どもの頃の母や父は、そしてぼくたちもまた、確かにこの種の言葉を使っていたのである。
いつの日からか、言葉は無残な崩壊を始める。
日本語教育に関わっている者たちでさえ、たとえば大学やその他の日本語教育機関で先生と呼ばれている者たちでさえ、恐ろしいほどの言葉遣いを平気でする者たちがいるし、日本という国の税金で運営をしている公的な組織のスタッフにも下品で乱暴な言葉遣いをする者が少なからずいるのである。
ぼくはその種の者たちと同席することがあると、ほぼ五乃至六分程度で胃腸の調子が悪くなり、トイレに行きたくなってしまう。どうしてこのような温かみがなく下品で、自分のことしか考えないような輩が先生と呼ばれるような、あるいは公的な仕事をする者として働いているのだろうと寒気を覚えるのである。そういった者たちはできる限り国やその他の権威に擦り寄り、他者の誹謗中傷を好物として屯している。擦り寄られた者たちも、他に持つべきプライドもないため、気持ちの悪い笑いを浮かべながら薄ら寒い仲間を形成する。
もっとも、そういう者たちの言葉遣いはその者たちの顔つきやものの考え方に合致しており、すなわち悪寒を覚えさせる均整が取れてはいる。
そういった大人たちの言葉の乱れが子どもたちに影響を及ぼさないはずはない。
特に母親たちの言葉遣いの崩壊は目を覆いたくなるほどなのだ。
次のような若い母親たちの子どもに対する言葉遣いは、もはや犯罪ではないかとさえぼくには思える。
「おい、ほら、そんなことしたらだめだって言っただろッ!」
「やめろよッ、あのおじさんに怒られるだろッ!」
「ッたく、さっさとしろよッ!」
「馬鹿じゃないの、まったくッ」
「やめてよッ、ママの洋服が汚れちゃうでしょッ。これ高いのよッ」
ある少年がクラスメイトに
「馬鹿ッ、死ねッ」
などという言葉をかなりの頻度で使うので、ある日、その子の母親に聞いてみた。
その子の母親は日本人で、父親は英国人である。英国で生まれたその子の日本語は母親からしか入ってこない。そのことを指摘すると、きっと私が時々叫んでいるのだと思います、とのこと。その母親にはさまざまな事情があったに違いないが、それでもここでしっかり認識しておくべきことがある。
母親とは何か、ということである。
母親も確かに一人の独立した人間である。そしてすべての人間が独立した存在であり、そのことはもちろん尊重されなければならない。
しかしながら、すべての人間が独立した存在であると同時に社会的な存在であるということも事実である。
人は一人では生きていけない。それはつまり、人一人の存在はさまざまな意味でその人間以外の存在に何らかの影響を与えているということである。
そのことについての自覚あるいは認識が必要で、とりわけ母親は子どもにとって極めて重要な存在である。
子どもの命が母親の胎内に芽生えたその日から母親の存在は子どもにとって最も近く、重く、重要なものとなる。
言葉を換えれば、子どもはまずは母親とともに生きるのである。母親の生をなぞるように、生きるということを始めるのである。
子どもにとって母親とはそういった存在である。
母親とは、子どもというもう一人の独立した人間の存在に直接関わる特別の存在なのである。
その母親の用いる言葉の世界が貧しく、あるいは醜く屈折したりしていると、子どもの世界は自ら歪んでいくだろう。子どもが内側からねじれていったりはしないのだから、責任の所在は明らかである。
言葉はまなざしである。真っ直ぐにものを見つめようとする姿勢を子どもは母親からまずは学ぶことになるのだ。(次回からは「父親」)
(November, 2002)
No. 29 子どもたちに今、何が必要なのか その4 母親(4)
「母」という漢字は女という文字の中に乳房を表す二つの点が配されて出来上がっているが、この「ハハ(母)」という言葉の語源はといえばさまざまな説がある。
「ハシ(愛)」の首音だけを重ねたものとするものや、子を「ハラム(孕む)」ところからとするもの、「ハラ(腹)」の意味であるとするもの、あるいは子どもが発音しやすく偶然発した音声「ファア」からとするものなどである。
きわめて動物的な、あるいは生理的なつながりが、本来、母と子どもの間にはあった。
しかし、<ヒト>が生物学的な存在から社会的な存在である<人間>へと進化したとき、そしてそれが現代社会という不必要なほどの複雑な人間関係を持ったとき、最も根源的な母と子の関係が明らかに変質化していく。
母と子の関係に、より人工的社会的な価値観が割り込んでくるのである。
たとえば子どもの通う学校は近年、母親の一つのステイタスのようなものとなっており、名門と呼ばれる学校に子どもが通っていれば母親もまた優れているとの評価を得ているような気がするのである。
だから、その名門と呼ばれる学校に子どもが通えるように、つまり名門校に受験で合格するようにと母親は必死であらゆる努力をするのである。そしてその努力の矛先は次第に低年齢化してゆくことになる。有名中学校に入る受験戦争は小学校へ、そして幼稚園へと降りていく。「お受験」などという滑稽な言葉を真剣な顔をして口にする高学歴の母親がいたりするので眩暈を覚えたりするほどだ。
そのお受験にいたるまでの幸せであるべきわずかなあいだもまた、たとえばまるで着せ替え人形のように一流ブランドの洋服や靴などで飾り立てられて、子どもたちは窮屈な呼吸をしなければならない。そのピカピカの子どもをペットか何かのように脇に携えて、母親は町を歩き、友達に会う。そういえば、犬に滑稽なベストなどを着せて得意げに歩いているご婦人を見かけることがあるが、さしずめわが子を犬同様に取り扱っているのである。本人の迷惑などお構いなしだ。
母親はもはや「ハシ」にサヨナラをして、わが道を行こうとしているのである。かつて母は子のためにわが身を捨てることさえできたが、いまや自分の愛人との生活のために邪魔になった子どもの命をその愛人と共謀して奪うことさえも母はできるようになった。
そんな母親は要らない。
子どもは母親のためにいい学校に行くのではない。だいたい大人たちが勝手に決めたいい学校なんてなんなんだよ、と子どもは叫んでいるのだが母親には聞こえない。
母親にとってのいい学校とはせいぜい受験成績のいい学校であって、どんな教育理念かとか、どういった先生たちがいるかとか、給食はおいしいかとか、運動場は広いかとか、その他のあらゆることはまったく関係ないのである。
勉強をしっかりしないと立派な大人にはなれないよ、母親を始め大人たちはそう叱咤激励し、子どもたちの司令官と化す。ところで母親の言う立派な大人とはどのような大人をさすのか。これがまたわからない。
我が家のお父さんはその立派な人間の範疇に入るのだろうか。その割にはお母さんはお父さんのことを立派だとは言わないし、それどころかなんとなく馬鹿にしているように感じられる。
隣の家の自動車はベンツで庭も広い。そのことがお母さんには我慢ならないことのようで、お父さんはいつもぶつぶつ言われている。
立派な人間とはどうやら一流と呼ばれている会社に勤めてたくさんの収入を得ている人のことのようだが、その一流と呼ばれている会社が突然つぶれたりすると、昨日まで立派だった人はその瞬間に立派ではなくなるということになる。つまり、立派であるということはたいしたことではなさそうだとある程度の思考能力があればすぐわかる。
その誰でもすぐわかることが母親にはなぜかわからない。
スーパー・マーケットですでに小さく切ってある野菜を買い、電子レンジで温めれば食べられる冷凍食品やそれ以下でもそれ以上でもないような食べ物、そんなモノを食卓に並べるような、そしてそれで胸を張っているような母親の論理は、子どもたちはとっくにお見通しなのである。出前の丼やピザがしばしば運ばれてくる家庭には、子どもの「ハラ」は存在しない。
母親の振りかざす理屈は論理性が恐ろしく欠落していき、しかしながら幼い子どもが相手なので修正されることなく強固になっていく。一般的にはそういうものを傲慢あるいは独善というが、母親自身にとってはきわめて筋が通っており、ゆえにパワフルだ。
父親の非力をあざ笑うかのように、母親から子どもたちに押し付けられるものは、限られた、そして陳腐な価値観で武装された卑小な夢と未来である。
母親はいつからこんなにも恐ろしく、無知で、傲慢な存在になってしまったのだろうか。
あるいは母親とはもともとこの程度の存在だったのか。(この稿、続く)
(April, 2002)
No. 28 子どもたちに今、何が必要なのか その3 母親(3)
母親は父親よりもほぼ一年前に親になる。
お腹の中にいる胎児の存在感、産道を通ってでてくる我が子の感触、生まれた子どもにお乳を与えるときの身体的接触、そこに母性本能や育児本能が目覚める。
父親がいわば精神的にあるいは論理的にゆっくりと親になっていくのに比べて、母親はもっともっと根源的に感情的に、そして肉体的にも疾うに親である。
子どものほうからしてみると、お腹の中にいるときから母親や父親の声を聞きながら無意識的に親の認識を始め、生まれてからの直接的な接触によって三ヶ月から六ヶ月の間に自分を保育する親の存在を意識的に認知するようになる。そして、その親に対して微笑を返すようになる。多くの場合、それは母親である。母と子の心理的絆が芽生えることになる。
この絆が大切である。一般にいわれるところの「人見知り」はこの絆が強まったことの表れである。親や親に準ずる親しい者たちこそが自分を守る存在であると認識するのである。
鳥類だと雛が卵から孵って数分後には目の前にいて動くものを親と認知する。いわゆる「刷り込み」(imprinting)といわれる現象である。これがヒトという動物の場合、この母と子の絆、つまり心理的結合が成立するためには、およそ一年がかかるといわれている。
この生まれて一年足らずの期間が、生物学的存在のヒトが社会的存在としての人間になる苗床となる。
この時期を幸せに過ごす子どもとそうでない子どもとでは、その子どもの心に与える影響には大変な違いが生ずるという。
乳幼児期の子どもから母親が去っていったり、あるいは日常の生活においても母親の精神状態が不安定であったりすると、子どもは回復不可能なほどに精神的ダメージを受けるともいわれている。
ところが昨今、生まれたばかりの我が子を授乳等の育児が嫌で、殺害したり虐待したりする母親が増えているという。夜中に起きてお乳をやったり、おしめを取り替えたりするのは確かに重労働であろう。授乳期の赤ん坊を抱えた母親の生活はその二十四時間を子どものために捧げているといっていい。加えて高度な現代社会にはかつてなかった複雑なストレスが蠢いている。その苦しさに耐えられぬ母親が増えているのである。
ぼくは動物学者ではないから正確なところは知らぬが、親が生まれたばかりの我が子を育児に疲れたなどという理由で殺すという事態や虐待するといった事態は動物として極めて特殊なのではないか。
文明はヒトを高等な動物に変えた。高等な文明社会を作った人間はしかし、その基盤としての母性本能や育児本能といったところから次第に病み、滅び始めている。
オンナという性に母という温もりが消えていこうとしているのだ。その結果、子どもたちは、その誕生の瞬間からあるべき愛を失いつつある。われわれの知性はそういったものに対してきわめて鈍感であり、あるいは鈍感を装っている。なぜなら、大人は自分自身が生きることですでに疲れきっており、我が子さえも守るエネルギーを有していない。
母親はすでに死んでいるのである。
子どもたちに今、何が必要なのか。
まずは、健康な母親である。では、健康な母親とは一体どんな母親を言うのだろうか。
もしも家庭を守り、専業として家事や育児を担当するのならば、そのことにプライドを持つことだ。
共働きや、女性が主たる生計担当者である場合はそれぞれの環境で工夫し対応すべきであるが、もしも専業で家庭を預かる場合は(そう決めたのなら)そのプロとしての自覚が必要である。
夜中の授乳もその他の家事も大変であるが、それは仕事なのである。
仕事と書くと冷たい響きがあるかもしれないが、仕事というものは冷たい行為ではない。お互いがそれぞれの力を出し合って支えあおうという行為であり、つまりは温かい。
さて、プロであるならば、その質的な向上を目指すための学習が必要であり、当然である。その学習を支えるものは、まず素直さである。
自分は完成された人間ではないという自覚である。ゆえに、学ぶことで少しずつ成長しようとするのである。
なにを学ぶか。
一日の時間の管理、労働の効率化や省力化、子どもへの言語コントロール、おいしい料理の作り方、どこにどんな花が飾ってあればよいか、などなどいくらもあるだろう。
こんなことを書くとお叱りを受けるかな。女性をなんだと思っているのか、勝手な封建主義だ、などと。
そんなことはない。ここに挙げた一例も、すべて極めて高度な能力を必要とするだろう。それらを貶め、あたかも外で働く女性のほうが優れた人間であるかのように位置付ける考え方のほうが、実に愚かな、稚拙な性差別者なのだ。(この稿、続く)
(November, 2001)
No. 27 子どもたちに今、何が必要なのか その2 母親(2)
一月から二月にかけて日本に出張した。全国の主要都市で講演をしたり、公開講義をしたりの旅である。
大阪で仕事を終えたぼくは、タクシーで伊丹空港へと向かった。次の目的地の福岡へ向かうためである。
タクシーの運転手さんは女性で、しばらく走ると運転手さんの身の上話が始まった。
「長男はイギリスに留学したこともありましてね、留学させたのがよかったのかどうか、なんとなく自分勝手な人間になってしまったような気もしてますわ」
「大学かどこかに留学されたんですか」
「いや高校ですわ。大阪の高校がイギリスに学校を作りましてね、その全寮制の学校に行きましたんですわ」
「その息子さんはどうされているんですか、今」
「大学を卒業して大きな会社に就職して、今、名古屋に住んでます。新しく家を建てたとかいって、見に来いなんていっていましてね」
「それはすばらしいじゃないですか」
「でもなんとなくね、それにその下の次男がこまった子でしてね」
「どうしてですか」
「ぐれてますねん」
「……」
「夫の経営する会社がこの不況でつぶれてしまいましてね、だからわたしもこうやって働くようになってしもたんですけどね。死のうかと思ったんですけどね、何とかがんばっとるんですわ。貧乏がようないようですわ。この前もその子が夫を、父親を責めよるんですわ、おまえがちゃんとしてないからうちが貧乏になったんやと。切のうて、切のうて」
「……」
「学校に行かんと、高校生なんですけどね、喧嘩したり物壊したり、もう地獄ですわ」
「それはいかんなあ、お父さんは会社をつぶそうと思ってつぶしたわけじゃないのにね」
「そうですわ、一生懸命に働いて働いて、それでもあかんかったんですわ、小っさい会社ですからね」
「……」
「でもね、そんな子でも、なんでか分からんのですが、かわいいんですわ、もうわたしはこの子が何とか立ち直ってくれるまではということで生きてるような気がしてます」
「時間があればその子に会いたいなあ、会って拳骨のひとつでもやりたいなあ」
「お客さん、先生かなんかですか」
空港でその運転手さんと別れたあとぼくは、母親はいつまでも子どもを胎内に宿して生きていくんだなあと思いながら、まあ、あのお母さんなら大丈夫だよきっと、と不思議な確信をして飛行機に乗り込んだ。
* * *
母親、この、子どもにとってはかけがえのない人たちに少しずつ変化が生じている。
子育てが面倒で、あるいは辛いからと子どもを虐待したり、それが原因で子どもの命を奪ってしまうような悲惨な事件が報道されることが増えてきた。
母親に何が起こっているのか。
ぼくはマザ・コンではないが、しかし母に対しては尊敬の念を強く抱いている。
こんな思い出がある。グリコ・ワンタッチカレーというものが新発売になる。チョコレートのようなものを溶かせば簡単にカレーライスが作れるというコマーシャルが盛んにテレビから流れると、なぜうちの母親はそれなのに粉から作ったりするのか不思議だった。
マヨネーズだってなぜ卵から時間をかけて作るのだろう、ぼくはそう思いながら母親の仕事を見つめていた。
料理というものはきちんと時間をかけて作るものだ、ぼくは今もそう信じている。だからぼくは、かつてこの「検証」において「味噌汁が永谷園のあさげであってはならない」と書いた(一九九一年)。
これは、「こんな母親が子どもを合格させる」というタイトルのつけられた、受験に奔走する母親をやや揶揄したものであった。当時これを読んだ方からいろいろな反応があった。
なぜ永谷園の「あさげ」ではいけないのかと電話をかけてこられた方まであった。インスタント食品が女性を不当な労働からどれだけ解放したかわかりますかといったお叱りも受けた。女性を虐げようとする封建的な考え方をしているのではないかと怒鳴られもした。
ぼくの研究所には数多くの女性たちが働いている。いずれもきわめて優秀で、男性でなければ仕事は勤まらないなどとはまったく思わない。というよりむしろ、女性のほうが仕事ができるのではないかと思うこともしばしばである。
ただ、現状ではまだまだ女性がそれらの家事や育児を担当することが多いので、ここでは一応母親と呼ぶことにする。
さて、その母親である。
子どもの教育にとって、母親ほど影響力をもっているものはいない。
ということはつまり、昨今の子どもたちの問題の責任の第一は母親にあるといってもよいことになる。
ただ、誰もそれをなぜか言わない。(この稿、続く)
(April 2001)
No. 26 子どもたちに今、何が必要なのか その1 母親(1)
少年法の改定、そして教育基本法の見直しと、日本の教育改革は少なくとも表面上はかなりの急ピッチで進められつつあります。
そしてそれらがそのように急がれる理由の一つとして、これも少なくとも表面上はマスコミをにぎわす少年犯罪が挙げられます。
確かにかつてこれほどまでに少年たちが殺傷に走った時代はなかったでしょう。
「なぜ人を殺してはいけないのか」といったテーマで月刊誌の『文藝春秋』が特集を組んだりもしています。
先日日本に帰った際、絵本やさまざまな創作活動を展開する五味太郎さんと彼のアトリエで三時間ほどじっくり話し合ったときも自然とこの話題になりました。
俺は殺されたくないから他人も殺さないんだよ、と五味さんは言っていました。
多くの人たちが『文藝春秋』の中でも同じような論理を語っています。
いずれにしても、ちょっと前までは問われることが絶対にないだろうと思われたことが実際に子どもたちの口から飛び出すようになっています。
子どもたちは一体何へ向かって走り始めたのでしょうか。
そして今、子どもたちに何が必要なのでしょうか。
数回にわたって、考えてみたいと思います。
*
このような状況下で、大人たちがどのようなことを考えているかといえば、大人たちは少年の心理分析や教育システムの見直しに忙しく、しかし実際の子ども一人ひとりと向き合っているかといえば決してそのようにはぼくには思えません。
むしろ子どもたちから遠ざかろうとしているようにさえぼくには思えます。
そんな中で、IT革命という言葉が一方で話題になっています。ぼくはこの言葉と教育や子どもたちの現在との関係が実は今の教育が抱える問題点を象徴しているように思えてなりません。
あれはどのくらい前のことだったでしょうか。
学校という社会にもようやくさまざまな先進機器が少しずつ入り始めた、およそ20年前ぐらいだったでしょうか。
文書作成が和文タイプライターでなされるようになり、それも手動から電動へ、そしてコピー機が大変な便利さを感じさせながら学校に登場します。
教育現場はつまり、ほんの少し前まではもっともっと原始的で、ことばを変えればもっと手作りの雰囲気にあふれていました。
現場の教師たちは目を見張りながらそういった新兵器の導入に取り組むことになります。
しばらくするといよいよコンピューターの普及です。
研究会での話題は、会のテーマからコンピューターのことについついそれてしまうような、そういったこともしばしばです。
わたしは教育現場の経験と、日本全国の教育現場の教師たちの指導の経験をもっていますが、教師たちはマテリアル開発や事務処理、そして研究の場にコンピューターを始めとしたそういったものを取り入れようと目を輝かし始めました。
学級通信や保護者への連絡もきれいに印刷された活字のものに変わりました。
かつては原紙に鉄筆を用いてのいわゆるガリ版印刷が、いつのまにか消えていくことになります。
わたしの右の中指にはまだ、鉄筆でできたペンだこが残っていますが、年々やわらかくなっています。
成績処理もコンピューターを用いてきれいに、たとえばさまざまなグラフ等を用いて表したものの方が保護者には気に入られるようになります。
そのほうが、優れた先生、教育熱心な先生として「保護者受け」がいいのです。
教師たちは、それほど機械に強い人たちばかりではありません。
そうしてもマスターするのに時間がかかります。
一方、機械に強い先生も、より美しい出来上がりを目指して工夫に熱心で、そのための時間が必要になります。
放課後、先生に相談に行ったり、質問に行ったりしていた生徒たちは、今忙しいからとの言葉で追い返されてしまうようになります。
こういった機械化の波は先生たちを間違いなく忙しくし、子どもたちとのふれあいの時間を奪っていったのでした。
教育の原点は、どんなに時代が進んでも、高度化しても、「人間と人間が向き合う場」ではないかとぼくは思っています。
相手の顔の表情を、目をきちんと見つめあいながら、生きた言葉を交わす場こそが、「人間という動物が人間らしさを維持していくための最も優れた教育方法」であると信じています。
しかし、教師たちは時の流れというものをとても気にし始めたのです。
親がいろいろと要求してきますし、予備校や塾が、そういった美しいプリントで、あたかもその美しさこそが教育の質を示しているかのような錯覚を押し付けてくるので、学校の先生たちはついついそういったものに引きずられてしまうことになります。
予備校や塾のこういった錯覚の巧みなビジネスは化は、たとえば実はいないお化けの存在で脅かしながらそのための、つまり必要ない対策を一生懸命させるあの手口そのままです。
また、教師たちの一般社会へのおどおどしたようなコンプレックスは、特にバブルの絶頂までの歴史の中でのそういったものは、不思議と蔓延していたのです。
デモシカ先生などとマスコミが余計な、そして無責任な命名をしてからというものは、教師たちは誇りというものをなんとなく持ちにくい職業人となっていったのでした。
さて、日本の教育改革においては、教育現場にコンピューターが配置され、たとえば小学校からどんどん取り組ませるようですが、ぼくとしてはこのことを心配しています。
ますます肉声を持った、つまり人間のまなざしを持った「先生」が必要でなくなるように思えるのです。
「肉声を持った先生」は、しかし機械に弱く、コンピュータに関しては子どもたちのほうがずっと早くマスターしていくに違いありません。
一方、機械に強い先生は、コンピュータの技術を教える事に夢中になり、コンピュータのインストラクターと変わらなくなります。あまりにも真面目に、そのことに取り組もうとするのです。
また子どもたちにしてみれば、学校でやらされるコンピュータの学習なんかより、家では自分のコンピュータを使って、もっともっと進んだことをしているのに、みんなに合わせたりしなくてはならないのでたまたま学校の授業に興味を失い、機械に弱い子はいじめられっこになったり、またある子は立派なコンピュータがないために肩身の狭い思いをしなければならなくなったり、コンピュータのソフトを買うために非行に走ったり、と心配事は数限りなく浮かんできます。
大人たちは一体子どもたちに、子どもたちの教育に何を求めようとしているのでしょうか?
大人たちが考える教育の意味とは一体何なのでしょうか?
コンピュータ教育で何を子どもたちに教えようとするのでしょうか。子どもたちに何を与えようとするのでしょうか。
コンピュータ教育で子どもたちの明日に何が豊かなものとして広がると考えているのでしょうか。
確かにリサーチにはコンピュータの威力は絶大です。
ぼくは時には二台のコンピュータを机の上においてほぼ同時に使い分けながら仕事をすることがあります。
日本に出張するときはノート型のコンピュータが最も頼りになる連れ合いです。
ですから、小学校におけるコンピュータ学習はそういった力をつけるのだといわれるかもしれませんが、そういったリサーチ中心の学習が果たして日本の教育の中で出来るのか、疑問です。
大人たちが慌ててITなどと叫び始めたのは結局、日本の経済力が世界に伍していけなくなるのではないかという不安感からではないのでしょうか。
戦後の日本を動かしてきたもっとも大きな価値観は、数字崇拝の論理です。
すべてを数字で評価していく動力が日本を先進国に押し上げてきたのです。
しかし、経済の発展が人間すべてを幸せにすることはできませんでした。
もちろん、どの家にも車があり、カラーテレビどころかビデオもDVDだって揃い、エアコンのおかげで夏も快適で、そういった暮らしはそうでない暮らしと比べて快適であるのは当然です。
でも、ぼくたちは何か違うという思いを心のどこかで感じ始めていたのです。
しかし、そういった思いも、溢れる物質の奥深い谷間に隠し、そういったものを無理やり忘れようとしていたのでした。
けれども、カルデラに溜まったマグマがいつか爆発するように、人間であるぼくたちはそういった何かひたひたと押し寄せてくる不安感にそのまま目を閉ざすことができなくなってしまっているのです。
ぼくたちに必要なものは、そしてぼくたちの子どもたちに必要なものは、一瞬にして世界とつながるインターネットではなく、時間をじっくりかけなければつながることができない、「人間の会話」ではないかと、強くそう思います。
子どもたちを大人の道具にしないでほしい、と思います。
強かな、にやりとした、屈折した笑顔に隠された計算尽くめの、そういった大人のいやらしさを、ぼくは憎みます。
子どもたちにとって何が幸せなのか、本気で考えなければならない、そういう時期に来ているのではないかと思うのです。
ITは、少なくとも、今の教室には必要ない。
いや、あってはならない。
ITと対峙する、「人間の言葉」を教室に呼び戻そう。
先生は、機械を通さない、血の通った言葉で子どもたちに語りかけよう。
そして、そういった言葉がぼくたち人間にとって一番大切なものだという知性を育てる先生でありたい。
負けてはいけない。
今こそ、ぼくたちは科学を本当の意味で支配しなければならない。
人間にとって幸せとは何なのかを問う教育の復権を、ぼくはそう主張したいのです。
(January, 2001)